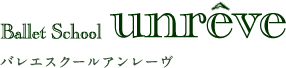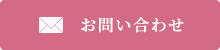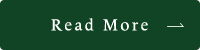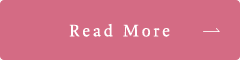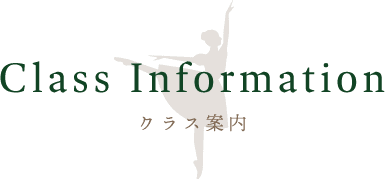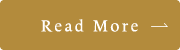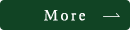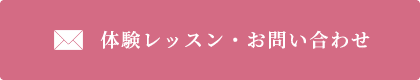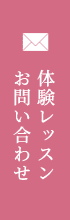-
みんなの夢があつまる場所に…
アンレーヴは、バレエの楽しさや感動をたくさんの人に知ってもらいたいという想いで立ち上げたスクールです。スクール名である『アンレーヴ un rêve 』とは、『ひとつの夢』という意味。
「あんな素敵な衣裳を着てみたい…」
「スポットライトを浴びて、舞台に立ってみたい」
「音楽にのって軽やかに踊れたら楽しいだろうな~…」
夢を追いかけるのに、年齢や経験は関係ありません。
バレエスクールアンレーヴでは、バレリーナを夢見る小さなお子さまから、趣味や健康のために踊りたい大人の方まで、おひとりおひとりに合わせたレッスンを受けることができます。
アンレーヴで、一緒にたくさんの夢を叶えましょう!


-
相模原スタジオ
Sagamihara
神奈川県相模原市中央区中央1-12-5
TEL: 042-860-2046
※レッスン中や営業時間外はつながりにくい場合がございます。
-
町田鶴川スタジオ
Machida Turukawa
東京都町田市野津田町1395
TEL: 042-860-2046
※レッスン中や営業時間外はつながりにくい場合がございます。
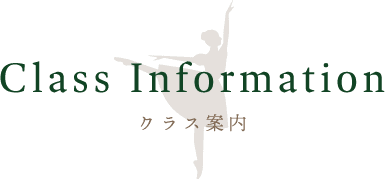
-
-
-
-
-
特別クラス
ヴァリエーションレッスン・ポアントレッスン等
-
ストレッチクラス・大人バレエ
健康バレエストレッチ

-
相模原スタジオ
神奈川県相模原市中央区中央1-12-5
TEL: 042-860-2046
-
町田鶴川スタジオ
東京都町田市野津田町1395
TEL: 042-860-2046
バレエを習いたい方、初心者歓迎!
※レッスン中や営業時間外はつながりにくい場合がございます。